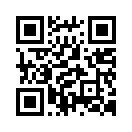2012年10月28日
市長選結果。
つくば市HPより
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/13/885/2810/3272/003275.html

1 当 市原 健一 無所属 現 36,010
2 いがらし 立青 無所属 新 28,048
3 桜井 よう子 無所属 新 16,864
4 山中 たい子 無所属 新 6,650
開票は終了しました。
投票総数 89,163
有効投票総数 87,572
無効投票総数 1,591
不受理総数 0
持ち帰り・その他 0
投票者総数 89,163
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/13/885/2810/3272/003275.html

1 当 市原 健一 無所属 現 36,010
2 いがらし 立青 無所属 新 28,048
3 桜井 よう子 無所属 新 16,864
4 山中 たい子 無所属 新 6,650
開票は終了しました。
投票総数 89,163
有効投票総数 87,572
無効投票総数 1,591
不受理総数 0
持ち帰り・その他 0
投票者総数 89,163
2010年12月18日
パブリックコメントについてのご意見

パブリックコメントとは?
パブリックコメント(Public Comment、意見公募手続)とは、公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に(=パブリック)に、意見・情報・改善案など(=コメント)を求める手続をいう。
公的な機関が規則などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すものである。通称パブコメ。
from ウィキペディア
以下、公民館廃止に関してのパブリックコメント制度について
掲載許可をいただいた意見です。
こういう不備があったために、今回は緊急で呼び掛けさせて頂くことになりました。
ぜひお読みください。
~~~~~~~~
私たちはより良いつくば市を創っていくには、行政と市民が共に協働して施策を作ることが、これからのつくば市にとって極めて大事なことだと考えています。
わたしは、市民と行政が共に施策をつくる制度であるパブリックコメントの手続きについて、また、パブリックコメントに寄せられた市民の意見が、今回の条例案に十分生かされていない、この2点について補足説明させていただきます。
公民館に関する基本計画案がパブリックコメントとして9月に意見を求められましたが、市民の意見集約も終っていない11月2日、市長がいち早く定例記者会見で「つくば市地域交流センター条例案」を12月議会に提出することを発表しました。11月24日が議会への請願書の締切日ですが、この段階ではパブリックコメントの実施結果は市民に公表されておりませんでした。
「パブリックコメント制度」というのは、「市民と行政が共に施策をつくる手続き制度」であります。
基本的な計画を策定する際には事前に案を公表して、市民の意見を聞き、寄せられた意見に対して市の考え方を公表し、それらの意見を考慮して最終案を作るという大事な手続き制度です。
意見を寄せた市民の声が反映されないまま「条例案」が上程されているのです。
集約結果が公表されたのは、議会開会日の11月30日のことでした。
このような条例案は、市民と行政が共に施策をつくる、とは到底言えず、行政に対する市民の不信感が募るだけではないでしょうか。
きょうの委員会には13団体という多くの市民団体が、公民館の行方を心配し慎重審議を求める陳情書が提出されています。
どうか市民の理解が得られるように本条例案を慎重審議し継続審議をお願いするものです。
2点目は、パブリックコメントに寄せられた市民の声について、
その内容を、私なりに整理して見ました、すると・・・
基本計画(案)に賛成する意見: 5件、9.6%、 反対: 16件、30.7%、
判らない・記述修正・時間をかけて討議: 13件、25%、
要望事項・どちらともいえない: 18件、34.6%、となっています。
パブリックコメントに寄せられた意見は: 反対意見、記述修正、時間をかけて討議が
全体の55.7%を占めています。 賛成意見は、わずか9.6%であります。
これらの意見を考慮すれば、議案は否決されてしかるべきであります。 時間をかけて討議、の
25%を考慮すれば、継続審議とすることが、妥当であると判断いたします。
委員のみなさまの真摯なご議論を期待して,私の説明とします。
有難うございました。
2010年12月18日
公民館廃止!?委員会の様子。。。

みなさま、以下、
公民館の条例について検討された委員会に参加された方より
掲載許可を得まして報告させてもらいます。
~~~~以下報告文章~~~~
つくば市地域交流センター条例案について
きょうは、環境経済常任委員会の傍聴、有難うございました。また、公民館の行方を心配してくださっている多くの市民の皆様にお礼と報告を申し上げます。
結論から言えば、公民館を改編する「つくば市地域交流センター条例案」は、反対3名、賛成4名で環境経済常任委員会で可決されました。
それにしても13団体が名前を連ねた慎重審議を求める陳情書は、議員・行政執行部に大きな圧力になったと思います。
高野議員まで請願の各項目を請願者に説明したのか?と行政担当者に問い質していました。
市民ネットの永井悦子議員、共産党の橋本けい子議員には、ご尽力をいただきお礼申し上げます。
有難うございました。
請願者発言が認められたことは、開かれた議会にする上で突破口となると思います。
亀山大二郎、元市議さんにも請願者発言ができるよう、事前に協力をお願いしていた事もあり、発言を認める委員が多く、吉葉茂委員長が発言を許可してくれました。
議員席から発言が許され、
手続き上に不備があること、
パブリックコメントに寄せられた市民の声が反映していないこと、
そして13団体が提出している慎重審議を求めた陳情書について発言しました。
パブリックコメントの意見は、
条例案賛成は、わずか9.6%、条例案に反対あるいは時間をかけて討議が55.7%であり、
条例案には、市民の声が反映していない事を指摘しました。
このことから言っても、本条例案は否決されてしかるべきであり、
条例案が市民の声を交え討議されるよう継続審議を主張しました。
それにしても、議事の進め方が何故このようになるのか?
意識的かもしれませんが、条例案を先に討議し、採決した後に請願書採択となり、そこで請願者発言を委員会に図ったのです。
議案討議中、2回も請願者発言を挙手で要請したにも係わらず無視され、社会常識では考えられない議事進行が行われました。
条例案を賛成多数で採決した後に、私の発言を許可したのです。
いくら請願者が発言しても採択に影響せず、ただただ発言させてやる、という議事運営にはあきれはててしまいました。
こんな形骸化した運営では、いつまでたっても市民の声は生かされないことになります。
でも、きょうの初めての請願者発言の許可が突破口になって、今後に生かせる大きな第一歩になればと思っています。
13団体が連帯して市民力を発揮したように、市民の声が直接、議会に反映できるような、力強いつくば市を創っていきましょう。
2010年12月17日
2010年12月14日
公民館有料化! 慎重検討陳情文書

ということで、陳情書を2010年12月16日付で
つくば市議会に提出することとなっています。
賛同団体を募っております。
ぜひみなさん、個人・団体で検討していただき、
この問題に対して慎重検討を求めることになりましたら、
ご連絡ください。
変えなきゃ連絡先
kaenakya.t<☆>gmail.com
(<☆>を@に変えてください)
また、この問題の発信をご協力いただければ幸いです。
すでに5団体ほどの連名にはなる予定です。
~~~以下、提出予定 陳情文章~~~~
「つくば市地域交流センター条例」の慎重審議を求める陳情
つくば市の公民館は「社会教育法」に基づく施設として設置され、地域の「実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」(社会教育法20条)ものとして運用、利用されてきました。
具体的事業内容は、定期講座の開設、討論会・講習会・講演会等の開催、図書の利用、体育・レクリエーション等に関する集会の開催、施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること等、住民の生活全般に係わる幅広いテーマをカバーするものとなっています。
この度、つくば市は、この公民館を廃止し、施設を地方自治法第244条に基づく「地域交流センター」に改編する「基本計画」及びその実現のための「つくば市地域交流センター条例」を議会に提出しようとしています。
私たちは、「つくば市地域交流センター基本計画」及び「つくば市地域交流センター条例(案)」には、以下に記すような問題と課題があると考えています。条例を拙速に策定することなく、市民の理解を得られるよう、慎重な審議を要望いたします。
1.条例公表までの手続き上の問題
つくば市は9月に「つくば市生涯学習施設基本計画(案)」についてパブリックコメントを実施しました。しかしその意見集約も、市民の意見に対する市側の説明もないままに「つくば市地域交流センター基本計画」及び「つくば市地域交流センター条例」が議会に提出されました。
こうしたことは、つくば市が「パブリックコメント制度」を軽視し、制度を形骸化させているのではないか、との疑問を持たざるを得ません。 これでは「行政と市民の協働によるまちづくり」というつくば市のあり方に反することになります。
また、この件について、公民館運営審議会は開催されておらず、生涯学習審議会の審議も不十分のまま、理由の説明もなく、見切り発車しているように見えます。
2.地域交流センターに転換しなければならない理由が不明
基本計画では、転換の理由を「社会教育法に基づく公民館では多様な市民のニーズに的確に応えられない」ため、としています。しかし、社会教育法第20条(前記)は公民館の活動を幅広く規定しており、基本計画で掲げているセンターの活動は、すべて公民館でも実施可能なものです。
3.提案されている「つくば市地域交流センター条例」の問題点
1)第7条(使用の許可の基準)5項で、「市長が不適当と認めるとき」は使用が許可されないと規定しています。市長の認可というようなあいまいな基準を設定することは、市民活動への行政の介入を招くことになり、社会教育法にも違反しています。また条例の第1条「市民の自主的な活動の促進を図り、もって豊かで活力ある地域社会を形成する」趣旨にも反することになると思います。
2)第9条(使用料の免除)では、一般市民団体の活動は「原則有料」で、免除はないということになります。ボランティア活動や学習会など毎週会合を開いている団体も少なくない現状で、経済的負担から活動を縮小・断念することにもなりかねません。これはまさに条例第1条に反する結果を招くと思います。
4.つくば市地域交流センター条例では明記されていないことから生じる問題点
1)センターに置かれる職員について明記されていません。つくば市公民館条例では第3条に「館長及び必要な職員を置く」としています。公民館主事等の教育的職員が配置されていないセンターでは、市民の学習権や自治的活動が十分に保障されないのではないと、危惧しております。
2)センターの活動に関し、利用者の意見を行政に伝える組織の規定がありません。公民館の場合は「公民館運営審議会」の設置が規定されています。そのような組織がない場合、利用者の意見、要望、苦情などはどのように運営に反映されるのでしょうか。利用者の声を受け止める組織がないようでは、センターがまちづくりの中心となる『コミュニティーセンター』の役割は果たせないと思います。
3)つくば市地域交流センター基本計画に述べられている内容が、条例には反映されていません。たとえば、センターの施設のあり方として、基本計画では、市民の学び、地域の活力、世代間交流、地域内交流を促す施設とすることが示されていますが、条例では、その内容については一切述べられていません。
以上のことから、私たちは、たとえ公民館がつくば市地域交流センターに転換されたとしてもそれが「市民にとってより使いやすく、地域住民の生活をより豊かにし、住民の自主性と自治の精神を育み、地域コミュニティーの中心的存在」になるよう、条例について、時間をかけて、関係する審議会や市民の意見を十分に聞き、つくば市の将来のために、慎重に審議して下さるよう、お願い致します。
以上
2010年12月14日修正
Web上で見やすくするために要点を強調するように修正しました。
赤字の部分を修正しました。
現在のところ、6団体が賛同しています。12月16日に市役所に提出しに行く予定です。
賛同できる方はぜひ連絡お願いします。
kaenakya.t<☆>gmail.com
(<☆>を@に変えてください)